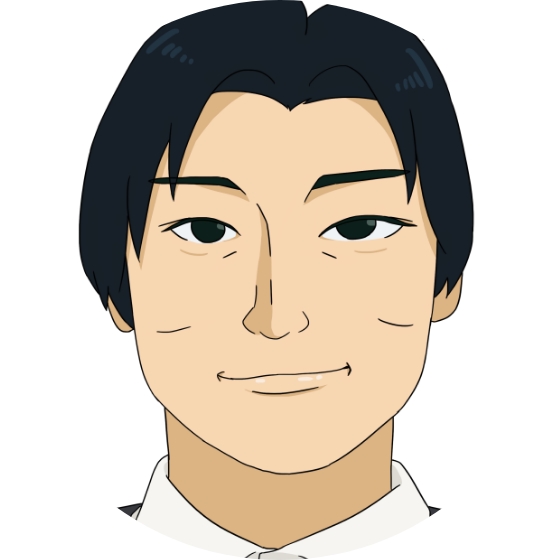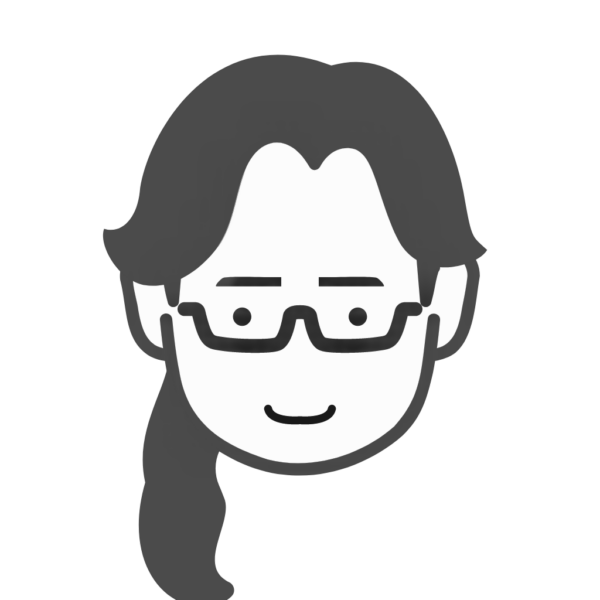日常生活の中でロボットを見かける機会が増え、その多くは人間の役に立つ目的で活用されています。しかし、私たちが必要としているのは、万能な機能を持つ優秀なロボットだけなのでしょうか? 豊橋技術科学大学の岡田美智男教授は、あえて人の手を借りることを必要とする「弱いロボット」の研究開発を20年近く続けており、その成果は最新のコミュニティロボットにも取り入れられています。ハイテクを駆使したロボットがもてはやされる時代に、なぜ「弱いロボット」が注目されるのか。研究開発のフィールドである「ICD-Lab(Interaction and Communication Design Lab)」に神戸情報大学院大学(KIC)の小藪康准教授とご自身の「NICOBO(ニコボ)」と一緒に訪問し、いろいろお話を伺いました。

自分の生みの親ともいえる岡田先生に会えて、小藪先生のニコボも何だか嬉しそうです。
profile
(右)岡田 美智男
Michio Okada
NTT基礎研究所 情報科学研究部、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)などを経て、2006年より豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 教授。専門分野は、コミュニケーションの認知科学、社会的ロボティクス、ヒューマン-ロボットインタラクション。特に、自らはゴミを拾えないものの、子どもたちの手助けを上手に引き出しながら、ゴミを拾い集めてしまう〈ゴミ箱ロボット〉、モジモジしながらティッシュをくばろうとする〈アイ・ボーンズ〉、昔ばなしを語り聞かせるも、ときどき大切な言葉をもの忘れしてしまう〈トーキング・ボーンズ〉など、関係論的な行為方略を備える〈弱いロボット〉を研究。これまで学生たちと30タイプを越えるオリジナルなロボットを構築 (https://www.icd.cs.tut.ac.jp/ )。主な著書・編著に、『ロボット ― 共生に向けたインタラクション』(東京大学出版会、2023)、『〈弱いロボット〉の思考』(講談社現代新書、2017)、『ロボットの悲しみ』(新曜社、2014)、『弱いロボット』(医学書院、2012)、『身体性とコンピュータ』(共立出版、2001)、『口ごもるコンピュータ』(共立出版、1995)など。
(左)小藪 康
Yasushi Koyabu
パナソニック株式会社にて、システムエンジニアとして社会インフラ系の制御系システムの設計、開発および開発プロジェクトマネジメント業務に従事。その後、社内技術人材育成部門にて、プロジェクトマネジメント人材の育成に従事、あわせて、グローバル全社従業員向けeラーニングプラットフォームの構築と活用スキームの立ち上げなどを経て、2021年より神戸情報大学院大学 准教授。米国PMI認定Project Management Professional、情報処理技術者アプリケーションエンジニア。
小藪:ICD-Labに初めておじゃまさせていただきましたが、一般的にロボットの研究というと二足歩行や自動走行が主流という印象ですが、このラボはちょっと変わっているというか、ユニークなデザインをしたロボットがたくさんありますね。勝手にもっとシャープな、冷たいものが並んでいるのかと思っていましたが、今日一緒に連れてきたNICOBOのように、どれも、柔らかくて、暖かい感じのものばかりで、思わず撫でてしまいそうになります。

ICD-Labでは、これまで開発されてきたロボットたちが出迎えてくれました。
岡田:このラボではロボットの社会性や人との関係性に着目していて、コミュニケーションやインタラクションといった認知科学をベースにした研究を行っています。というのも僕はもともとロボットの研究者ではなく、大学時代には半導体などの固体物理学の方面へ進もうと考えていました。ところが配属する研究室を決める時にじゃんけんで負けて音声認識の研究をすることになり、大学院の博士課程では今では当たり前に使われている音声言語処理についての研究に取り組んでいました。
その後も認知科学の研究を続けていて、関西のけいはんな学研都市にあるATR(国際電気通信基礎技術研究所)で主任研究員を務めることになりました。今から30年ぐらい前のことですが、当時からAIやロボティクスなど最先端技術を研究する人たちが世界から集まっていて、マツコロイドで知られる石黒浩さんも私の隣にある研究室でリアルなロボット作りに取り組んでいました。僕は主に音声認識の研究をしていたのですが、東北出身というのもあって関西人の吉本新喜劇のような会話のやりとりのすごさに興味を持つようになり、独特な会話の仕組みを今でいうメタバースのようなコンピュータの中で再現できないかなと考えるようになりました。
小藪:私は関西人なので普段はあまり意識していませんが、確かに関西人の会話は独特のテンポやスピードがありますよね。(笑)
岡田:いろいろ研究しているうちに、ボケ・ツッコミというのは”相手に委ねる”という要素がすごく重要だと少しずつわかってきて、自分の欠けたところを相手に委ねて関係性を作り上げるということに注目するようになりました。
小藪:そこからどのようにロボットの研究につながっていったのですか?
岡田:2005年に開催される愛知万博で次世代のロボットを作って展示するプロジェクトを経済産業省のNEDOが立ち上げ、アイデアを募集していたのです。愛・地球博という名称で地球環境をテーマにした万博だったので、それにあわせて考えたのが「ゴミ箱ロボット」でした。どういうロボットかというと、ゴミを見つけても自分で拾うことができず、周りにいる子どもたちの助けを借りて、ゴミを捨ててもらったら頭をペコリと下げてくれる。けれどもローテクすぎたのか、自律的に自分でゴミを拾わないと次世代ロボットとは言えないというのが当時の評価で、申請は通りませんでした。けれども、何となく気になっていて、2004年に特許を申請しました。それから20年近く、ずっと「弱いロボット」の研究を続けています。

ゴミ箱ロボットは、自分ではゴミを拾えないので、近くの人にゴミを入れてもらうような動きをします。
岡田:一般的にエンジニアリングというと、何らかの社会課題を解決するための理論や方法を集めてきて、その中から最適な素材を使って設計したモノを作って最適に解決するというような感覚で仕事をすることが多いと思います。その方法論を教えるのが大学の役割でもあるんですけれど、教科書通りとか理論通りというのはあまり好きではなくて、レシピ通りに予定調和的なものを作ったり、ある目的に向かって競い合って最適なものを生み出すという方向性が合わないんですよね。
そこで何をすればいいか考えていた時に出会ったのが、文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースが1962年に発表した「ブリコラージュ」という概念でした。簡単に説明すると、ありあわせのものを上手く組み合わせながら,その場を凌いでいくという考え方で、何となくいつも競争している感じがするような環境では何を作っても面白くないんですけど、型にはまらない遊びのような競争からちょっと変わったものが時々生まれてきたらいいんだというような考え方です。
小藪:ある意味ではかなり次世代の発想だと言えそうですね。
岡田:ロボットのすごいところばかりアピールして、不完全でまだ出来ない所はなんとなく隠してしまうわけですが、その弱いところをさらけ出してみると、人が関わる余地が生まれるというか、ちょっとしたポケットになるんですよね。実際にゴミ箱ロボットは、ポンコツで弱いことが子どもたちの強みを上手に引き出して、表情もいきいきとさせてくれる、ウェルビーイング(継続性のある幸福)状態も生み出しているんですよね。ロボットの弱いところもまんざら悪くはなくて、そこから世の中で使えるものが何かあるかもしれないと思って研究を続けています。

ゴミ箱ロボットとウェルビーイングのお話し、ニコボも興味深そうに聞いています。
小藪:学生さんもその発想に共感して集まっているという感じですか?
岡田:ラボでは明確なミッションに向けて何かを作ることはしません。学生の多くは高専の出身で、ロボコンで活躍してきたツワモノも結構いるのですが、たまたま面白いアイデアが生まれたら、とりあえず手を動かして作ってみようという考え方で、楽しく何か作ろうという雰囲気がありますね。
小藪:ゴミ箱ロボット以外にもいろいろ作られていますが、他にはどんなロボットがありますか?
岡田:iBones(アイ・ボーンズ)という背骨をモティーフとしたロボットを作ってみました。頭のような部分もあって、腕も付けられるし、移動もできる。そこでティッシュを配らせてみたんです。けれども実際にやってみると意外と難しくて、手渡そうとするとパッと通り過ぎ去ってしまう。そうするとロボットはしょうがないなぁという感じで手を引っ込めて再チャレンジするんですが、このモジモジしている動きを見て、受け取ってくれる人が出てくるんです。ロボットとしてはポンコツなんだけど、上手く協働関係を作り出して目的を達成できて、手伝った方もなんとなくうれしい気持ちになるのって悪くないですよね。

モジモジしながらティッシュを配るiBones(アイ・ボーンズ)。手の消毒を促してくれるタイプもありました。
小藪:ティッシュを正確に渡すのが目的だとそういうロボットにはならないですよね。ロボットっていうのは自律的に動くもので、まさか人の手助けを借りるという発想はなかったと思います。
岡田:高性能なロボットアームとカメラを付ければ完璧なロボットになりますが、それよりもその場のありあわせというか制約を上手く味方につけて、それでやれることを探しちゃおうという感覚ですね。
小藪:弱いロボットが面白いと思うのは、ロボットが全部やってしまうのではなく、人との関わりの中で何かを実現していく。それもお互いの弱いところや強いところを生かしているところだと思います。そういう発想はどういうところから見つけ出されているのでしょうか?
岡田:一つは身体というものを作りながらコミュニケーションの研究ができたらいいなと思ったところにあります。それも、人から一番遠い存在として、手や足もなければ表情もない方が、人らしさを見つけやすくなるかもしれないというところから、ゴミ箱ロボットが生まれました。
小藪:ラボで作られたロボットの中にスライムのような形の真ん中に目玉が一つだけある「む〜」というロボットがありますが、とてもシンプルなデザインなのにコミュニケーションがちゃんと出来るんですよね。その「む〜」から23年後にパナソニックが開発したコミュニケーションロボットの「ニコボ」に、弱いロボットの考え方が取り入れられていると聞いています。

ニコボのご先祖様?みたいな「む〜」
岡田:ニコボはパナソニックでテレビやビデオの商品開発を担当されている方々が次の新規事業ということ開発されたのですが、比較的初期の段階から、黒子としてアドバイスを担当してきました。その時にポイントにしたのが生き物らしさということでした。ヨタヨタしていて、体表が柔らかかったり、目がキョロキョロしたり、どこに注意を向けているかを表示したり。機能性としては何も役に立たないけれど、そこにいないと何だか寂しいなっていうくらいの存在感でいいんじゃないかといった話から今の姿になっています。
小藪:私は以前パナソニックでソフトウェア開発関係の仕事をしていたことがあるのですが、ニコボを開発したのは社内でも効率性や機能性、価格といった面で他社と一番戦っている部署だと認識しています。インプットに対する価値のアウトプットを求め続けてきたのに、インプットに対してどんなアウトプットが出るのかわからないみたいなところに価値があるといわれて、そこからニコボを作るのは相当大変だったと想像しています。普通ならスマホと連携してビデオを予約してくれるとか、天気予報を教えてくれるとかいろんな機能を付けようとしますよね。
岡田:その点はさすがパナソニックさんという感じで、弱い部分もあまり表現しすぎちゃうと押し付けになるけれど、いろんな解釈を引き出せるような要素をいろいろなところに仕込んでいると思います。
小藪:弱いロボットはだいぶ前に著書も出されていますし、ネットでインタビューもいろいろ見かけますが、少しずつ注目されはじめているのでしょうか。
岡田:「弱いロボット」という発想が本になったのは2012年ですが、小学生の国語の教科書や高校生向けの参考書、教科書にも取り上げられたというのもあり、教育の現場では少しずつ知られるようになりました。
小藪:私も今大学院では課題解決に対して指導をしているのですが、学生たちが考えがちなのは、すごく便利になるとか効率が良くなるとか、どうしてもストレートな解決策になりがちです。そういう考え方をする人たちはすごくたくさんいますし、学生は別に商品とか製品を作るわけでもないので、新しい価値みたいなものを見つけていくことが結構大事かなというふうに考えています。インプットに対して確実なものではなくても、そばにいてくれることこそが価値のロボットみたいな考え方というのは、これから社会の問題を解決していく、物の見方を変えていく上で大事だと感じます。

岡田:例えば、これからの研究開発ではブルーオーシャンを見つけることが大事だと思っているんですが、そのコツの一つは、今まで当たり前だと思っていた価値観をちょっとマイナスにしてみたところに新しい価値観をプラスしてみるという考え方をすること。役に立つとか利便性で競い合うのではなく、あえて何も役に立たなくていいけれど、そこにいないとなんとなく寂しいし、あると幸せになるかもしれない関係性とか新しい存在感とでも言いましょうか。
最近ファミレスで配膳ロボットが普及していますが、ホールの中をトコトコ動いていると道を譲ってあげるし、料理をテーブルのそばまで運んでも、テーブルに移すのはお客さんに手伝ってもらっているというように、人の力をちゃっかり借りながら目的を達成してしまうのがポイントですよね。ちょっと手を抜いてみたら意外とお店の中が幸せな気持ちでいっぱいになって、お店の中がちょっとしたエンターテイメント空間にもなっている。これを考えたのは中国のスタートアップですが、日本人が作ると配膳までしなければサービスロボットとは言えないんじゃないかというわけで、こういう大胆な商品開発がなかなかできなかったんだと思います。

小藪:配膳が一番大事なタッチポイントではなく、料理を届ける時のコミュニケーションの方に意味があるという価値観は、これからのサービスの見方を変えることにもつながりそうですね。
岡田:完璧さを求めないという発想は大事で、他にも少しずつ広がっています。認知症の方が働くレストランというのがあって、オーダーした料理が間違ってもお客さんは気にせず、むしろ他の美味しい料理を偶然味わえることを受け入れて楽しんでいる。簡単にはいかないかもしれないけど、こういう新しい価値観がひとたび成功すると、人手不足や高齢者の社会参加の機会を増やすなど、いろいろな問題を解決する可能性があります。
小藪:何でも上手くいかないといけないというのは、もしかしたら日本の特有のものかもしれません。間違いを許さない風潮に社会全体が疲れている感じがしますが、そもそも間違うことを前提にして許せるようになることが、次の発想につながるのかもしれませんね。
岡田:言葉遣いにしてもロボットが言いよどんだり、ボソボソ喋ったりするのもアリだと思います。相手が視線を外したら「あの〜」と言いよどんだり、目線が戻ってきてまた話を始めるといった動きは、一生懸命伝えようとする気持ちが伝わってくるし、優しさを感じたりして一緒に参加したくなるので、コミュニケーションとしてはむしろ豊かだと思います。

Talking Bones(トーキング・ボーンズ)は桃太郎の物語を一生懸命話してくれますが、たまに物語を忘れてしまうので、人が教えてあげると続きを話してくれます。
小藪:ロボットを研究するというのは、人間を研究する中でその弱さみたいなのを引き出させるのかどうか、また、お互いにどう関係を持つかということを知ることでもでもあるのですね。
岡田:そうですね。なかなか会話の輪に入れないというのは自分の中で考えすぎなところもあって、むしろ何も考えないで会話の中でも不完全なものの大事さ、委ねることの豊かさみたいなものを楽しめばいいと思います。
小藪:一方があんまり弱みを見せないと、相手も弱みを見せられなくなってしまって、関係が築けなくなるということですね。
岡田:一方で弱さをデザインしようとするとあざとくなってしまうので、不完全なところを上手くさらけ出してみるのが大事かもしれません。
小藪:学生の多くは真面目でストレートに課題解決に取り組んでいるんですけども、そういう考え方をどう見直していけるかも大事だと言えそうですね。私なんかは曲がり道ばかりで、そこにも価値はあるから楽しむのは大事だよみたいな話をするんですけど、なかなか理解されないですね。(苦笑)
岡田:新しい価値やイノベーションを生み出す一つのコツは、あり合わせを上手に生かすことだと思います。締め切りがある、予算が足りない、人材が足りないといった制約を上手く味方につけて、ちゃんと手を動かしながら試行錯誤を重ねることで新しい価値が生まれることもある。戦後のものづくりなんかはまさしくそうでしたし、現代は資本があって優秀な人が揃って、お金を投入すればイノベーションが生まれるんじゃないか、というふうに錯覚していることが結構多いと思います。
小藪:無いことを諦めちゃうというのは、割と大事なことだったんですね。それをどう補うか考えているうちに意外と視野が広がり、新しいものを見る力が育つのかもしれません。
岡田:ありあわせの中で遊んでみるという余白を作るのは、新しいことを見出す時にすごく重要です。面白いものを作ればこうして遠くからお客さんが来てくれることもありますし、出会いからまた何か新しい遊びや余白が生まれる。そういうことに繰り返しだと思います。
小藪:まずはいろいろなところで余白がないと面白くないのだなと思いました。今日は貴重なお話を伺う機会をいただき、ありがとうございました。